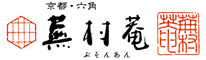【蕪村菴俳諧帖53】鳴かぬ螢に思いを託す
◆愛でる東洋 忌む西洋
狼男が徘徊するのは満月の夜。
狼になるのは男に限らないそうですが、
変身するには月の光を浴びるのだといいます。
漫画などでは魔女が月を背景に飛ぶ図像をよく見かけます。
魔女には月が似合うのでしょうか。
月の女神「ルナ(luna)」に由来する
英語の「ルナティック(lunatic)」は「狂人」を意味する言葉。
フランス語の「リュネール(lunaire)」は
「気がふれた/狂気の」という意味でも使われます。
ヨーロッパには月を見つめると気がふれるという言い伝えがあり、
上記のような月を語源とする言葉や伝承はそれを裏付けています。
月は忌むべきものという考えが定着していたのでしょう。
しかし日本にはこういう子守歌があります。
○世間おそろし 闇夜はこわい 親と月夜は いつもよい
忌むどころか月夜を喜んでいます。
親が世間から子どもを守ってくれるように、
月は闇夜の恐怖を除いてくれるのです。
日本に限らず、古来東洋の人々は月を愛(め)で、 詩人や歌人は月を眺めては詩や歌を詠んできました。
◆やさしいお月さま
理由はわかりませんが、 わたしたちの月は昔からやさしかったようで
○三日月は ちよつと咲うて入にけり 露川
沈んでいく月が笑った(「咲う」は「笑う」に同じ)というのです。
沈む直前の月は笑っている口に見えませんか。
露川(ろせん)の代表作のひとつです。
○中なかに ひとりあればぞ月を友 蕪村
「なかなかに」は「むしろ/いっそのこと」の意。
月をともに楽しむ友人を「月の友」と呼びますが、
独りでいれば月を友にできるではないかと。
蕪村は几董(きとう)宛の書簡にこの句を引き、
そのほうが月を楽しめると記しています。
○こがらしに 二日の月の吹きちるか 荷兮
二日月は三日月より細く、三日月より早く沈みます。
それを凩(こがらし)が吹き散らすと見たのです。
荷兮(かけい)はこの句が評判になったため、
「凩の荷兮」と呼ばれるようになりました。
○夏の月 蚊を疵にして五百両 其角
「春宵一刻価千金」といいますが、夏の月夜はその半額だと。
その理由は蚊に刺されるのが玉に疵(きず)だから。
そんなことを言いながら、其角(きかく)は夏の月を楽しんでいます。
わたしたちの祖先が四季を問わず
月を見上げて愛でてきたことのうかがえる句ばかりです。