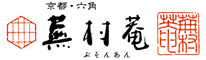【蕪村菴俳諧帖41】遊郭島原と蕪村
◆お大尽の贅沢空間
京都に「丹波口(たんばぐち)」という駅があります。
由来はかつてこの辺りに丹波に向かう街道の入り口があったため。
老ノ坂を経由して丹波に通じていたのですが、この道は
島原の遊郭に通じる道でもありました。
今も残る目印は大銀杏。
その先にいかにも遊郭らしい築地(ついじ=塀)があり、
さらに先に細かい格子が印象的な、立派な建物が現れます。
これが現在重要文化財になっている揚屋(あげや)です。
揚屋というのは太夫(たゆう)などの高級遊女を呼んで遊ぶ店。
指名された太夫は置屋(おきや)から、美しく着飾り
禿(かぶろ=見習い)や新造(しんぞう=新人遊女)などを引き連れ、
しゃなりしゃなりと「揚屋入り」しました。
客は悠長にそれを待ち、思う存分散財したわけです。
一般庶民には到底無理な、贅沢な遊びです。
揚屋にはその贅沢さを際立たせる舞台装置が
さまざま用意されていました。
その一つが襖絵(ふすまえ)で、この揚屋には池大雅、
丸山応挙らの傑作が遺されています。
なかでも目を惹くのが蕪村の『紅白梅図』。
現在は襖から外されていて一枚の絵として鑑賞できますが、
かつては当時のスター絵師の作品が室内調度になっていたのです。
◆遊女へのまなざし
蕪村は島原の遊女たちにどのようなまなざしを向けていたのでしょう。
『美人図自画賛』にはこのように書かれています。
花どりのために身をはふらかし
よろづのことおこたりがちなる人のありさまほど
あはれにゆかしきものはあらじ
○花を踏みし草履も見えて 朝寝かな
「はなどり」は「花鳥」から転じて男女の営み、
「はふらかす」は放り出すこと。
日常のさまざまなことを怠りがちな遊女のようすが
哀れで心が惹かれるというのです。
○住吉の雪にぬかづく 遊女かな
先述の大銀杏は島原の住吉神社境内にあったもの。
遊廓は廓(くるわ=曲輪)といって塀で囲まれており、
遊女は自由に外に出られませんでした。
物詣(ものもうで)は廓内の住吉しかなかったのです。
雪の中に詣でた遊女は何を祈っていたのでしょう。
○傾城は のちの世かけて花見かな
傾城(けいせい=高級遊女)の花見。
見た目は華やかでも、遊女は来世の幸福を願って花を見ている。
自由の身に生まれ変わり、心おきなく花見を楽しみたいだろうと、
蕪村は遊女の心情を思いやっています。