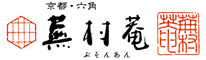【蕪村菴俳諧帖13】切れ字十八字
◆切れのあるなし
物事が終ったり勝負に決着がついたりするのを
よく「けりがつく」といいますね。
和歌や俳句の最後には「けり」がつくことが多いので、
「けりがつく」が終りを意味する慣用句になったといわれます。
○磯ちどり 足をぬらして遊びけり(蕪村)
○道のべの木槿は 馬にくはれけり(芭蕉)
○水鳥の おもたく見えて浮にけり(鬼貫)
ラ変助動詞の終止形、というと難しいですが、
句が完結するだけでなく詠嘆のニュアンスが加わるのが特徴です。
俳諧では「けり」を切れ字と呼びます。
ほかには「かな」や「や」が代表的な切れ字。
これらは句中や句末で意味を切るはたらきをするもので、
句の途中に使えばそこで一呼吸置くことになります。
○荒海や 佐渡に横たふ天の河(芭蕉)
○いな妻や 佐渡なつかしき舟便り(蕪村)
○朝寒のけふの日なたや 鳥の声(鬼貫)
「切れがある」というのも、切れ字が効果的な句を
そう言ってほめたことに由来するのだとか。
◆切れ字の種類
句中や句末で意味を切るはたらきをする切れ字。
すでに南北朝時代の連歌師、二条良基(よしもと:1320-1388)が
切れ字の効果について述べ、発句は切れるべきだとしています。
「切れ」はずいぶん古くから重視されていたのです。
その良基が選んだといわれるのが《切れ字十八字》という基本18種。
以下に蕪村の用例とともに列挙してみます。
(蕪村に見当たらなかったものは他の俳人の句から選びました)
1)かな……○菊は黄に 雨おろそかに落葉かな
2)もがな…○我頭巾 うき世のさまに似ずもがな
3)ぞ………○ねぶたさの春は 御室の花よりぞ
4)か………○ゆふがほのそれは髑髏歟(か) 鉢たゝき
5)や………○すみずみにのこる寒さや うめの花
6)よ………○夏河を越すうれしさよ 手に草履
7)けり……○宿の梅 折取ほどになりにけり
8)じ………○折くるゝ心こぼさじ 梅もどき
9)ず………○芭蕉去て そのゝちいまだ年くれず
10)つ………○古河の流を引つ 種おろし
11)ぬ………○冬の梅きのふやちりぬ 石の上
12)らむ……○紅梅の落花燃らむ 馬の糞
13)いかに…○出て三日 人ならいかに猫の恋 (貞佐)
14)し………○花に舞ハで帰るさにくし 白拍子
15)け………○壬生寺の猿うらみ啼け おぼろ月
16)せ………○毛見の衆の舟さし下せ 最上河
17)へ………○笠程な庵と思へ 初時雨 (涼袋)
18)れ………○旅人よ笠嶋かたれ 雨の月
もちろん切れ字はこれ以外にもあり、
切れ字を使わなくても切れのある句を作ることはできます。
句がどこで切れているか、どんな効果をあげているか、
考えながら鑑賞してみるのも面白いですね。